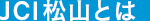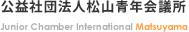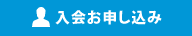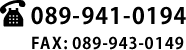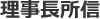 松山青年会議所 第74代理事長 泉田 洸からのメッセージ
松山青年会議所 第74代理事長 泉田 洸からのメッセージ
対話を通じた多様性と組織力の融合
我々は今、かつてないほど多様な価値観が共存する時代に生きている。グローバル化やデジタル化が急速に進み、社会は効率性を追い求める一方で、人と人とのつながりは見えにくくなり、対話の機会も希薄になっている。このような時代だからこそ、メールやSNSの文章だけでは読み解けない感情や価値観を、対話を通じて理解し合い、まちづくりに取り組める強靭でありながらもしなやかな組織にしたい。
松山青年会議所には、73年間にわたり先輩諸兄姉が築き上げてきた組織という確かな土台がある。そして、我々には一人ひとりが持つ新たな発想力、現代のテクノロジー、多様なバックグラウンドという力がある。これらを掛け合わせ、「新しい可能性を生み出す発想力」と「共感を生み出す実行力」を兼ね備えた、唯一無二のまちづくり組織になることができると私は考える。
我々は長年にわたって紡がれてきた関係諸団体とのネットワークや、青年会議所メンバーをはじめとした多くの仲間たちと語り合える環境に恵まれている。そうした環境を活かし人々と日々情報を共有し、対話を重ねることで、多様な価値観を理解し、強靭な組織となる。理想を語り、挑戦し続けるその先にこそ、明るく豊かなまつやまの未来があると私は信じている。我々の可能性は無限であり、仲間と進むこの一歩一歩が、未来のまちを創っていく道となる。
挑戦
松山青年会議所には20歳から40歳までという年齢制限がある。仕事の実務も忙しく、多くのライフイベントが重なる最も忙しい年齢設定の中で、限られた時間で活動する組織だからこそできることや学べる事がある。
私はこの松山青年会議所に入会して、わずか5年間で、7つの責任ある役職を経験する機会をいただいた。その都度、業務への支障や日常生活への影響を考え、不安で押しつぶされそうになった。しかし、その先にある成長した自分の姿を尊敬する諸先輩方に照らし合わせ、挑戦と成長の機会と向き合い挑戦を続けてきた。
「挑戦する」とは、まだ達成したことのない目標や、慣れない分野、新たな課題に、自ら進んで取り組むこと。挑戦には失敗や困難がつきものだが、その過程で得られる経験や人とのつながりが、自分自身を大きく成長させてくれる。
我々は新たな組織像のもと、人々のつながりの強さを感じるまちづくりに挑戦する。
-
未来に影響を与えるリーダー育成
-
長年にわたり青少年の健全育成に貢献し、我々に感動とノウハウをもたらしてきた「わんぱく相撲」は青少年に限らず、我々が組織として更に成長する可能性を秘めている。この「わんぱく相撲」をカリキュラム化し、在籍年数の浅いメンバーと共に運営することで、青少年の健全育成と共に主体性とJAYCEEとしての誇りを育みたい。また2025年度に構築された「管理者養成プログラム」は、在籍年数の短いメンバーが増加する松山青年会議所において、運営基盤の強化に大きく寄与した。これを継続開催する意義は極めて大きく、今後は現状反映させた内容へと進化させ、より効果的なリーダー育成を図っていく。我々は、青少年の健全育成と会員育成の新たな可能性に挑戦する。
-
我々が世界を近づける
-
我々は国際青年会議所(JCI)の一員として、世界との接点を得る機会に恵まれている。2026年、新潟で開催されるJCIアジア・太平洋会議(ASPAC)は、国内にいながら国際の風を肌で感じられる絶好の機会であり、その学びの多くを地域へ持ち帰ることが我々の責務である。長期化する円安の影響により海外の目が日本に向いている今、我々が築いてきたベトナム・ダナンJCとの友好関係を更に強固なものとし、まつやまの可能性を世界に広げるための国際ビジネスの糸口を掴みたい。我々は、まつやまを世界とつなぐ存在として、自らの手で国際への入口を切り開く。
-
日本有数の祭を目指して挑戦する
-
松山春まつり(お城まつり)は松山青年会議所の一大公益事業として実績を積みながら、松山の歴史・文化と共に松山青年会議所の存在を地域に刻んできた。総来場者数も年々増加し、周辺地域からの注目度は着実に高まりを見せているものの全国での知名度は決して高くはない。松山の春の風物詩となった松山春まつりを日本でも有数の祭として昇華していくためにも、今一度松山の歴史や文化の意義を再確認・発信するとともに、知名度を高めるためのブランディングが必要となる。我々は幅広い世代の心を動かす祭を開催し、松山の歴史や文化を広く発信し、松山の賑わいを創出する。松山の春を、日本の春へ。我々の挑戦はまつやまの未来を創造する力となる。
-
届けたい想いを、もっと届くかたちで
-
デジタル化の進展とSNSの急速な普及により、広報の手法は多様化し、その可能性は日々広がりを見せている。これまでも松山青年会議所では、広報誌「わかつばき」や公式SNSを通じて組織の魅力を発信してきたが、その効果にはまだ大きな伸びしろがある。我々の発想力やテクノロジーを駆使すれば、更に効果的な広報活動ができると確信している。今こそ広報の在り方を見つめ直し、時代に即した手法を調査・研究し、固定概念にとらわれず、松山青年会議所の魅力をより効果的に伝える広報を展開していく。
-
熱く本気の姿に人が集う
-
過去数年間にわたり、減少傾向にあった会員数は復調の兆しを見せつつある。人口減少が進む中で、2025年度に先輩諸兄姉に尽力いただき構築したシニアクラブとの連携による複合入会システムは、現役メンバーの熱き会員拡大活動があったからこそ結果が生まれた。我々の活動や想いを共有できる仲間を増やしていくことが、今後の組織拡大と希望ある未来を創ることにつながる。しかしながら、会員拡大に対する意識には未だ個人差があり、準備を図っていくための仕組みづくりが必要である。我々はこの築かれたシステムをより精度の高いものに磨き上げるとともに、更なる現役メンバーへの拡大運動の重要性を浸透させながら組織として会員拡大の機運を高めていく運動を熱く推し進める。
-
次代へつなぐ、しなやかな組織運営
-
総会の開催、定款の管理、会員名簿の整備は、長きにわたり松山青年会議所に受け継がれてきた規律であり、組織運営において極めて重要なものであるからこそ、その時代に合わせて変化を続けてきた。目まぐるしく変わる社会情勢の中で時代の変化や社会の要請に応じて、柔軟に見直しを図る必要がある。青年会議所として変えてはいけない基本を堅持しつつ、より効率的かつ的確な運営方法を模索し、これからも必要とされ続ける組織としての体制づくりに挑戦したい。
-
ヒト・モノ・仕事が生み出す好循環を実装する
-
我々が住み暮らすまつやまは、若者の転出超過による人口減少という深刻な課題を抱えており、その要因は多岐にわたり、即効性のある解決策は存在しない。だからこそ、課題を的確に捉え、具体的な試みを継続的に実行していくことが求められる。地域の若者がまつやまの企業を知らず、企業の魅力や価値が十分に伝わっていない現状は、転出超過の一因であり、まつやまの青年経済人や企業人が集う我々が、地元企業の認知拡大に留まらず、企業価値向上のきっかけづくりに率先して取り組む必要がある。我々と産官学民が連携し、ヒト・モノ・仕事が好循環を生み出すインパクトのあるまちづくり運動を展開することが、まつやまの未来を切り拓く大きな一歩になると信じている。
-
たからの山まつやま、もう一歩深く
-
新型コロナウイルス感染症の収束以降、まつやまを訪れる観光客は右肩上がりで推移しており、周辺地域からの誘客を図る各種取り組みはさらなる増加が期待されている。しかしながら、現状は他の観光地と比較してまつやまを訪れる観光客の滞在日数は短く、まつやまの観光の魅力は伝わり切っていない。まつやまには多くの伝統ある文化や豊かな自然があり、その価値は決して地域内に留まるものではなく、まつやまの未来を切り拓く可能性を秘めたたからの山であると確信している。多様性が尊重される現代だからこそ、既存の枠にとらわれない新たな観光資源を創出し、「帰りたくなるまつやま」を実現したい。
-
結びに
-
人生には多くの決断の機会があり、その決断次第で人生は大きく変わる。そして厳しい変化を求められる時代ほど成長の機会があり、青年会議所での活動はその成長への試練と挑戦の連続である。私は松山青年会議所 史上初の決断と挑戦を続ける。明るく豊かなまつやまの実現を目指し、共に立ち上がり、挑戦し続けよう。
我々は今日、昨日の自分を超えていく。挑戦
~昨日の自分を超えていけ~